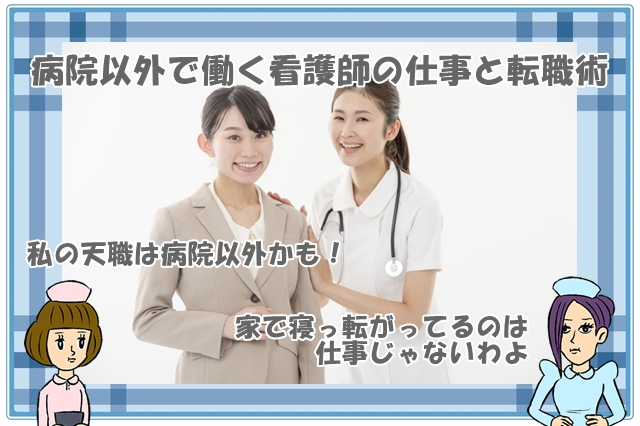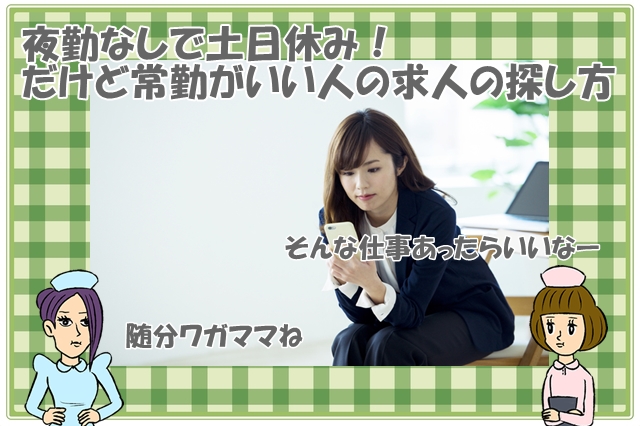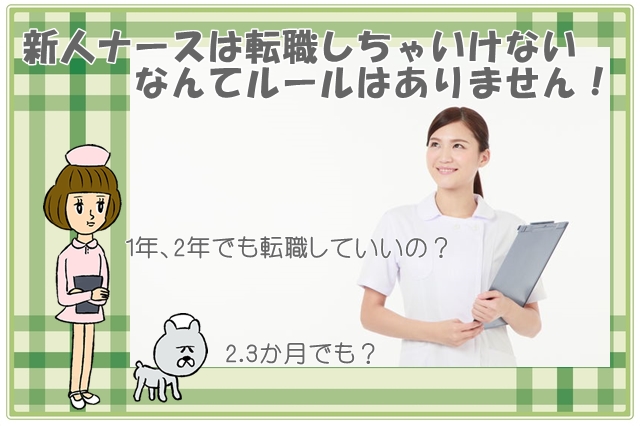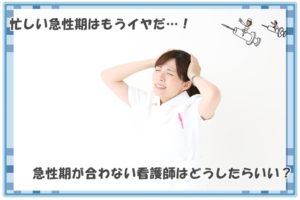慢性期病院の看護師ってどうなの?急性期との違いをわかりやすく解説!
PR 来世は犬になりたい元ナース
来世は犬になりたい元ナースシバタダダ
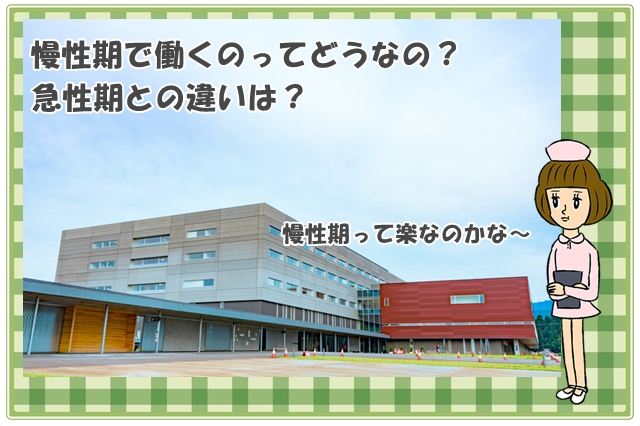

こんにちは!病院のイメージで話しをすれば、急性期病院は「忙しい・大変・看護師がバリバリ活躍」って感じですよね。それに対して慢性期病院って「ゆったり・ルーチンワーク・寝たきりの患者さんが多い」って感じでしょうか?
じゃ、『みかん』さん、急性期病院と慢性期病院の違いを説明して下さい。
具体的に急性期病院と慢性期病院の違いを説明してと言われると、ほとんどの方がとまどってしまうのではないでしょうか?
知っているようで意外とわからない「急性期病院と慢性期病院の違い」について、ここでおさらいしながら慢性期病院の看護師の働き方についてお話ししますね。
急性期と慢性期の違い、キーワードは「病院機能報告」
そうですね、まず「病院機能報告」から考えてみましょうか?
厚生労働省は予想される少子高齢化を踏まえて、限られた医療資源を有効に活用しようと団塊の世代が後期高齢者になる2025年までの医療体制改革の完成を推し進めています。
その大きな柱である「病床機能報告制度」では、病棟の機能を「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の4つに分けて、毎年病棟単位で報告することになっています。
今後少子高齢化がもっと進めば、寝たきり等の長期入院患者の増加が予想され、病床不足が考えられます。
そのため「病床機能報告制度」を設けて現状の機能報告の結果から、将来必要になる病床数を予想して、各地方の病院の病棟機能を今のうちに割りふりしちゃおう!と簡単に言えばそんな政策です。
つまり、急性期病棟の看護師の働き方、慢性期病棟の看護師の働き方の違いがハッキリ定義されているんですよ。
急性期病院・急性期病棟とは?
「病床機能報告制度」では急性期でも機能により二つに区分していています。具体的にどこが違うのでしょうか?簡単に説明しますね。
高度急性期機能
急性期の患者に対し、状態の早期安定に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能:救急救命病棟、ICU(集中治療室)、NICU(新生児集中治療室)など
高度急性期機能に入院する患者さんの場合、生命の危機状態なので医療も看護も密に行わなければなりません。
急性期機能
急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能
急性期機能に入院する患者さんの場合、手術を受ける患者さんや、ICUで管理するほどではないが急激な病気発症に対し入院が必要な治療する場合ですね。
ひとことで「急性期病院・病棟」と言っても機能の違いによって看護業務・ケアの内容が変わります。
急性期病院の看護師の特徴と仕事内容は?
高度な看護スキルとアセスメント能力が必要
急性期は患者さんの状態が安定しないし、急変も起こりやすいですよね。特に高度急性期機能にあたるICUなどで仕事をしている場合は、看護技術・処置も高度です。
看護師は患者の状態の変化をすばやくキャッチできるアセスメント能力を求められます。
キャリアアップには急性期病院がピッタリ!
看護技術、アセスメント能力が身につくので看護師としてのスキル向上が期待できます。看護技術をきちんと習得してキャリアを伸ばしたいと考えている場合、急性期病院で働くのは大きなメリットです。
基本的に忙しく、残業も多い
急性期は他に比べて残業や時間外が多いです。患者さんの状態がどう変化するかは予想が難しいもの。急変や緊急入院など基本的に忙しいです。
急性期についてさらに詳しく知りたい方はこちら→急性期はキツイだけ?やりがいは?急性期病院で働く看護師のメリット・デメリット
慢性期病院・慢性期病棟とは?
じゃあ、今度は慢性期病院についても考えてみましょうか?
「病床機能報告制度」では慢性期機能は以下のように定義されています。
- 長期に渡り療養が必要な患者を入院させる機能
- 長期に渡り療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能
『れもん』さん良いところに気が付きました!慢性期病院は実は2つの体制に分かれています。
- 吸引など医療行為な必要な慢性期の患者:「医療療養病床」
- 寝たきりのお年寄りなど介護中心の患者:「介護療養病床」
慢性期といっても、「医療が必要」か「介護中心」かによっても看護師の仕事内容が変わるんですよ。
慢性期病院の看護師の特徴と仕事内容とは?
慢性期病院の看護師のメリット
●ルーチンワークで看護技術・処置が少ない
慢性期病院は予測できない事態が起きることも少ないので、毎日のスケジュールが決まっていることが多いです。
慢性期病院・病棟の看護技術・処置の例:
- 呼吸に関する看護技術:喀痰、経鼻・口腔内吸引、酸素マスク、カニューレを使った酸素療法など
- 食事援助に関する技術:食事介助、経管栄養法(経鼻経管栄養、胃ろう)など
- 与薬に関する技術:内服介助、注射
- 排泄介助:トイレ介助、おむつ交換、浣腸・摘便・導尿・ストーマケアなど
- 清潔に関する介助:入浴介助、清拭、病衣交換など
- 歩行介助・体位変換、車椅子移動など
- 患者や患者家族へのケア指導
慢性期病院は処置も決まったものが多く、急性期病棟と比べるとたしかに時間の流れはゆっくりですね。
●患者さん一人ひとりにじっくり関われる
慢性期病院、病棟の患者さんは在院日数が長いため接する機会も多いです。患者さん一人ひとりに時間をかけて関われるのがよいところです。
患者さんの人となりを知ることができ、患者さん家族にお会いする機会も多いので今困っていることや悩みを聞き患者さんに合ったオーダーメードの看護を提供できます。
また、患者さんや患者家族へのケアの指導の機会も多く、必要によっては地域との連携のための連絡係になったりもしますよ。
●残業が少ないためプライペートが充実
慢性期病院・病棟は毎日のスケジュールが決まっていることが多いとお話ししました。急変が起こることが少ないので、残業が少なく早く帰れるというメリットがあります。
慢性期病院の看護師のデメリット
●看護スキルが伸び悩む
慢性期病院・病棟で働くのはいいことばかりじゃありません。スケジュールが決まっているということは、必要な看護スキル以外は学ぶ機会が少ないということです。
急性期のように色々な病態の患者さんを見る機会がないため、経験の浅い看護師さんの中には看護スキル習得のために急性期病院で働きたいと希望する場合もあります。
●介護療養病棟は廃止されることを考慮して
介護療養病棟は今後廃止予定なので、これから転職を考える方にはあまりおすすめではないです・・・
平成18年の医療制度改革の一環として、平成23年(2011年)までに介護療養病棟6万床、医療療養病床は約27万床のうち7万6,000床が廃止される予定でした。
しかし、切り替わりがうまくいかないため平成29年(2017年)末まで延長措置が取られていたのですが、さらに6年の追加延長措置が発表されました。つまり、宙ぶらりん状態なんです。
今後は「介護療養院」と呼ばれる新しいタイプの施設が誕生します。
こちらは介護認定が降りている患者さん対象で、要介護度4〜5の方は介護療養院Ⅰ、要介護度が軽度ならば介護療養院Ⅱに相当します。
看護師の働き方は、特別養護老人ホームのようになると思われますが、制度として発足したばかりで、なんとも言えないのが正直な感想。
このように介護療養病棟は改革の波にさらされています。医療改革制度の今後の動向に注目したいところですね。
参照:地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案
慢性期病院・病棟は患者さんと向き合える看護が魅力
慢性期の看護ってどう思いましたか?
そうですね。急性期と比べると残業が少ないので、ママさんナースにも慢性期病棟はおすすめですね。
患者さんとじっくり関わりながら看護をしたいと考えている方は、転職先に慢性期病院・慢性期病棟を考えてみるのもいいかもしれませんよ。
人気記事ベスト5
この記事を読んだ人は以下も読んでいます
登場人物
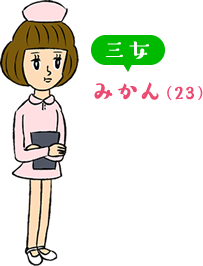
のんびりな性格の新人ナース。2人の姉の影響で看護師に。色々なことに疎く、生き方もなぁなぁ。
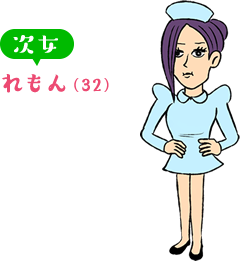
キャリア志向のナース。趣味はセミナー巡り。大の血管好きで血管愛好家という一面も。
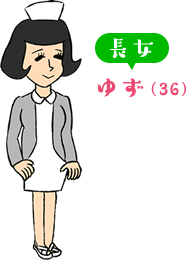
仕事と子育ての両立に励むママナース。2児の母。三姉妹の中で最もおっとりした性格。
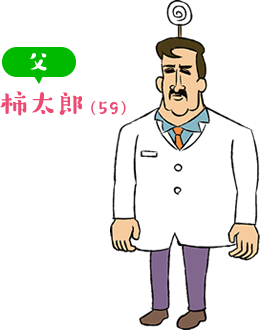
みんなに愛されるダンディな開業医。頭から生えてきた額帯鏡がチャーミング。
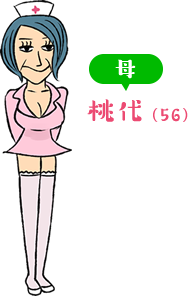
仕事も男も経験豊富なベテラン看護師。数多の男を落としてきた美脚は今なお衰えていない。
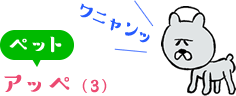
犬か猫かどっちか分からない正体不明のペット。自分もナースだと思い込んでいる。